これは冷静な分析などではありません。私の内から突き上げてくる怒りであり、この社会が正気を失っていく様を座視できないという焦燥そのものです。なぜ、多くの人々が口をつぐみ、なぜ、国民の代表であるはずの政治家までもが沈黙するのでしょうか。この根源的な問いを前に見て見ぬふりをすることは、私自身の生き方に反します。この記事に込めたのは、社会の現状に対する深い懸念であり、言葉を奪われた人々の声を取り戻したいという、やむにやまれぬ衝動です。
なぜ高市氏と原口氏の話から始めたのか
「たまたま異物入りのワクチンだったので、あとでお知らせは来たものの、相当長い間、不調に悩まされました」この発言に対し、政敵とも言える立場にある原口氏が、彼女の身を案じる姿がありました。
原口氏は、毎朝5時、早い時には4時台からXのスペースなどを通じて配信を行っていますが、そこで松下政経塾の後輩である高市氏の苦しみに心を寄せ、お見舞いの言葉をかけたのです。
政策においては明確に異なる立場をとりながらも、一人の人間として苦しむ相手を気遣う。これは、極めて自然な感情の発露です。
人間らしい温情に満ちたこの逸話を敢えて冒頭に置いたのは、「言論統制」という、人間性そのものを否定する冷酷なメカニズムに気づいていただくためです。
「政策が違っても人として心配する」という原口氏の姿勢は、記事を通じて私が訴えたかった、分断を超えた対話の象徴に他なりません。
この人間的な視点こそ、言葉がその機能を失った社会の冷たさを浮き彫りにするために必要なのです。
「反ワク」「デマ」が思考を停止させたメカニズム
この記事で最も解き明かしたかった核心の一つが、特定のレッテルがいかにして国民の思考を停止させ、本質的な議論を不可能にしてしまったか、というメカニズムにあります。
「反ワク」という言葉が出てきた時、私は強烈な違和感を覚えました。「デマ」という言葉も同様に、思考を止めるための、恐ろしく便利な道具として機能したのです。
情報量が多すぎると、人は逆に思考停止に陥るのでしょうか? これらの言葉がメディアやSNSで飛び交うようになると、人々は複雑な問題を深く考えることをやめてしまいました。
ワクチンに慎重な意見を持つ人々を「反ワク」の一言で片付け、「変な人がいる」と安心することで、自らは思考停止に陥っていきました。慎重派がどれだけ冷静な議論を求めても、その声は「デマ」というレッテルによってかき消され、届かなくなりました。
この言葉の武器化がもたらした最悪の結末は、「会話が終わり、言葉が奪われた」ことです。さらに深刻なのは、多くの人々が、自らの言葉と思考が奪われているという事実にさえ気づけなかったことです。
メディアやインフルエンサーは分断を煽り、ただ「冷静になって考えてほしい」と願う慎重派を、まるで社会に害をなす「害獣のように扱った」のです。
こうして、健全であるべき言論空間は完全に歪められてしまいました。そして、この言葉がもたらす思考停止の伝染病は、ついに国民の代表者であるはずの政治家たちをも沈黙させるという、より深刻で根深い病巣へと繋がっていきます。
沈黙する為政者たちへの失望と、私たちが本来あるべき姿
個人の言論が封殺されるだけでなく、国民の代表であるはずの国会議員までもが、この問題について自由に発言できないのです。
私は、この現状を明確に「異常」だと断じざるを得ません。
本来であれば、物事の真実を追求しようとする議員が多数派を占めているべきではないでしょうか。それが、私たちが目指すべき議会の姿であるはずです。
かつての「薬害エイズ問題」を知る世代であれば、当時とは比較にならないほど多くの人々が今、苦しんでいる現実に気づけるはずです。しかし、社会全体を巻き込む大きな声にはなっていません。
国民からは確かに声が上がっています。にもかかわらず、その声を正面から受け止めず、黙認しているのは「国会議員」たちです。国民の声から目を背け、保身に走る彼らの姿に、私は失望を通り越して、もはや一種の軽蔑さえ覚えます。
何のために国会議員をしているのでしょうか?
国民の生命と健康に関わる重大な問題から目を背け、沈黙を選ぶのであれば、その存在意義とは何なのか。
この根源的な問いは、単なる政治批判を超えて、私たちがどのような代表者を求め、どのような社会を築くべきかという、私たち自身の生き方の問題にも繋がっていきます。
記事に込めた個人的な信条
この記事は、単なる社会批評ではありません。それは、私自身がどう生きたいかという、極めて個人的な信条にも深く根差しています。
私がなぜ、沈黙が支配する空気の中で、あえて声を上げるのか。その理由は、この一言に集約されます。
自分が死ぬ直前に、「俺はこれだけはやった」「筋を通した」「恥ずかしくない生き方ができた」と胸を張って言いたい
見て見ぬふりをし、長いものに巻かれ、安穏と過ごすこともできるでしょう。しかし、それでは死の床で自分を誇ることはできません。
もちろん、完璧な人間など存在しません。時には人を傷つけ、間違うこともあるでしょう。だが、そうした「弱い自分、だらしない自分も含めて受け入れて、改善する努力」を続けることこそが、誠実に生きるということだと信じています。
この記事を執筆した行為は、私にとってその「筋を通す」ための一つの実践です。そして、この個人的な信条は、今や社会全体にとって重要な意味を持つのではないでしょうか。
一人ひとりが自らの信条に従い、恥ずかしくない生き方を選択する時、社会は初めて健全な姿を取り戻せるのではないかと、私は問いかけたいと思います。
熱意を取り戻すために
私が最も伝えたかった核心的なメッセージを改めて強調したいと思います。それは、安易なレッテル貼りをやめ、思考停止から脱却し、たとえ意見が違っても粘り強く対話を続けることの重要性です。
高市氏と原口氏のエピソードが示したように、私たちは政治的信条を超えて、一人の人間として他者を気遣うことができるはずです。奪われた言葉を取り戻し、冷笑を突き破るものは、理屈ではありません。人間の体温そのものです。
最後に、私は強く願います。政治家たちに、そしてこれを読んでくださった、私たち一人ひとりに。
もっと熱くなってほしい
冷笑や無関心に身を委ねるのではなく、自らの信じるもののために声を上げ、行動する。その熱意の総和だけが、この淀んだ空気を打ち破る力となるのですから。


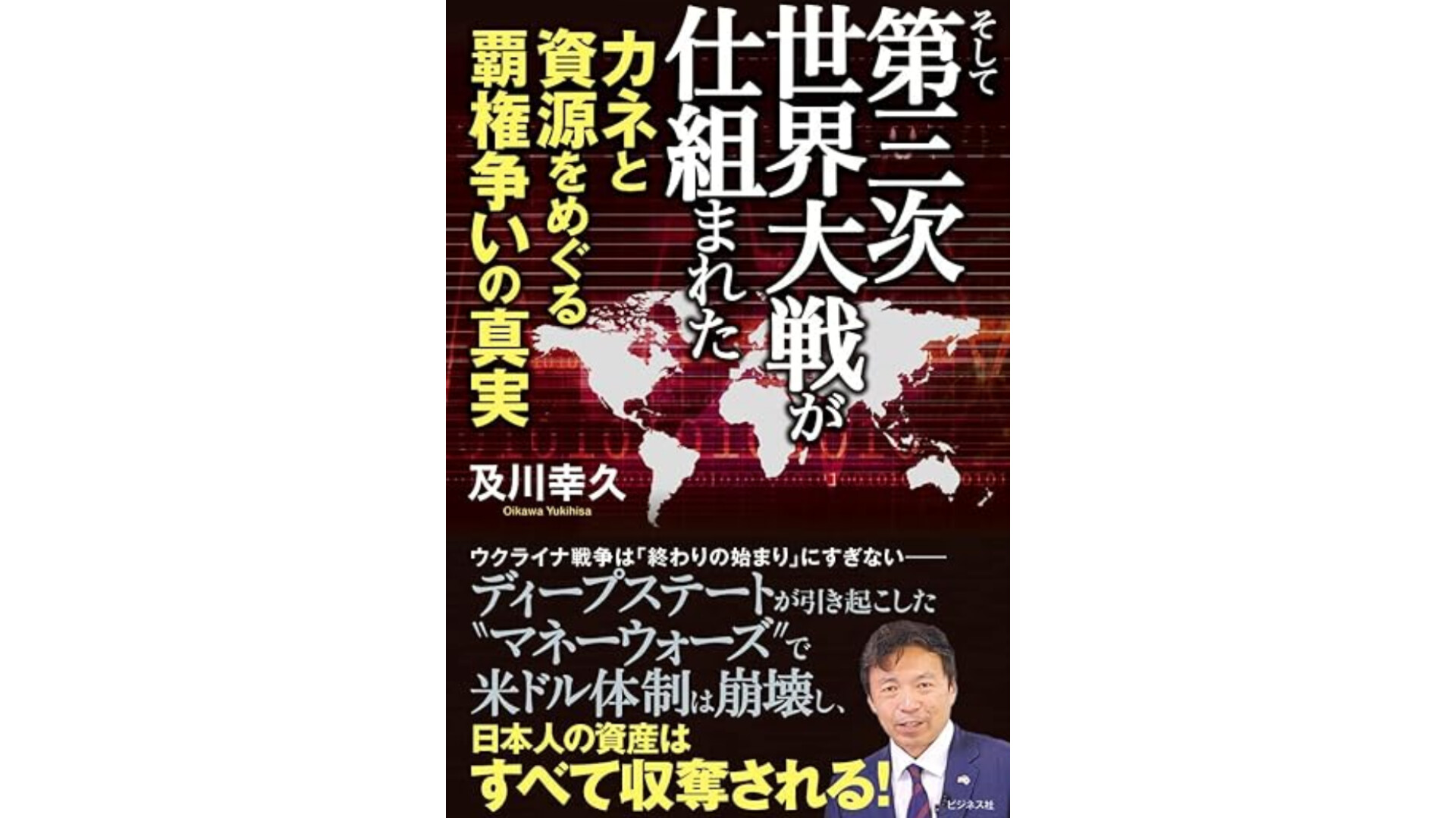
人気記事