漫画家・倉田真由美氏のSNS投稿をきっかけとして、女性の公人、特に政治家に対して向けられる特定の批判が問題となっています。この種の批判は、個人の資質や政策への正当な評価ではなく、ジェンダーに基づいたステレオタイプを強化し、公の場における女性の行動を不当に制約します。このような言説が拡散される現代において、その構造と問題点を分析することは、自由な公論空間を維持するためにとても重要です。
倉田真由美氏の投稿
(11月2日午後3時頃、Xでの投稿)
実際「女を使っている」と高市首相を非難した女性の多くが、過去を掘り起こされ「お前はどうなんだ」と言われてしまっている。「私は違う、でも彼女はそう」というご都合主義は通らない。だから、そもそも「女を使っている」などと侮辱的なことを決めつけ、SNSという公の場で言うべきではないのだ。
(11月2日午後1時頃、Xでの投稿)
それにしても高市首相など他人の挙動を「色仕掛け」とか決めつけるの、いかがなものか。ドイツのメルケル元首相は胸の谷間出しまくりだったけど、あれ、色仕掛け?本人の内心分からないのに決めつける他人がいるせいで、女がどれだけ不自由になるか考えてみてほしい。
倉田氏は、高市早苗氏のような女性政治家の言動を安易に「色仕掛け」と断じる風潮に疑問を呈しました。そして、対照的な例としてメルケル元首相を引き合いに出し、「本人の内心も分からないのに決めつける」行為が、結果として女性全体の表現の自由を狭め、社会進出の足枷となりかねないという本質的な問題を提起したのです。
批判者に跳ね返る刃:「お前はどうなんだ」という反論
女性が同性を「女を使っている」と批判する時、そこには複雑な力学が働いています。一見すると、それは公正な基準に基づいた批評のように見えるかもしれません。しかし、その実態は、しばしば批判者自身に跳ね返る諸刃の剣となります。この現象を分析することは、公の場で発言することの責任を理解する上で重要です。
事実、「女を使っている」と高市早苗氏を非難した女性たちの多くが、自らの過去の言動を第三者によって掘り起こされ、「お前はどうなんだ」という痛烈な反撃を受けています。この「ブーメラン現象」は、もはや珍しい光景ではありません。SNSという誰もが過去を検索できるオープンな空間において、他者に向けた批判の刃は、容易に自分自身にも向けられるのです。
この現象がもたらす問題は、批判そのものの説得力を失わせてしまいます。批判者が、他者を断罪したのと同じ文脈で評価され、矛盾を指摘されることで、本来議論されるべきであった政策や政治姿勢といった本質的な論点は雲散霧消します。そして後には、個人の人格をあげつらうだけの不毛な応酬だけが残されます。
この一連の帰結が示す教訓は明確です。他者を特定の基準で裁こうとするならば、自らもまたその基準によって裁かれる覚悟が必要となります。そして、その基準が曖昧で主観的なものであるほど、批判は説得力を失い、単なる個人的な攻撃へと堕してしまいます。この構造の根底には、これから論じる「ご都合主義」というべき心理が横たわっています。
根底にある「ご都合主義」の構造分析
「女を使っている」という批判の裏には、それを発する人物の心理的なメカニズム、すなわち「ご都合主義」が潜んでいます。この心理を深く理解することは、なぜこの種の論争が常に不毛な結果に終わるのかを解明し、より建設的な議論への道筋を探る上で不可欠です。
このご都合主義的な論理は、以下の極めて自己中心的なフレーズに集約されます。
「私は違う、でも彼女はそう」
この言葉が示すのは、「自分は客観的で公正な立場にいるが、批判対象である『彼女』は違う」という、根拠のない自己正当化の論理です。自分自身を例外的な棚に上げ、他者に対してのみ厳しい基準を適用します。これは、私的な会話の場であれば許されるかもしれませんが、誰もが目にするSNSのような公の議論の場においては、決して通用しません。
公共圏における言論の基本的な原則は、他者を批判するために用いた基準が、普遍的なものであり、当然ながら自分自身にも適用されるという点にあります。他者の内心を「女を使っている」と断罪するならば、自らの過去の全ての言動もまた、同じ基準で精査されることを受け入れなければなりません。この原則を無視した「ご都合主義」は、もはや批評ではなく、単なる感情的な侮辱に過ぎません。
このような自己正当化の論理は、いかなる建設的な議論も阻害します。それは対話の可能性を閉ざし、相手への敬意を欠いたレッテル貼りに終始するため、社会にとって何一つ有益なものを生み出さないのです。
SNS時代の言論に求められる責任と自覚
女性公人への「女を使っている」という批判を通して、その背景にあるブーメラン現象と、根底に存在するご都合主義的な自己矛盾を明らかにしてきました。この一連の分析が示すのは、現代のSNS時代における言論がいかに大きな責任を伴うかという、自明でありながら見過ごされがちな課題です。倉田真由美氏の結論を振り返ってみましょう。
「そもそも『女を使っている』などと侮辱的なことを決めつけ、SNSという公の場で言うべきではない」
この結論が重要である理由は、それが個人の尊厳と、より広い社会の健全性に関わるからです。他者の内心を憶測に基づいて断罪し、侮辱的な言葉で公に決めつける行為は、健全な批評の範囲を逸脱しています。それは、対象者の人格を傷つけるだけでなく、後に続く女性たちが公の場で活躍しようとする意欲を削ぎ、行動を萎縮させるという深刻な社会的影響を及ぼします。自由な言論は尊重されるべきですが、それは他者を根拠なく貶める自由を意味しません。SNS時代の言論には、これまで以上に深い自覚と責任が求められています。


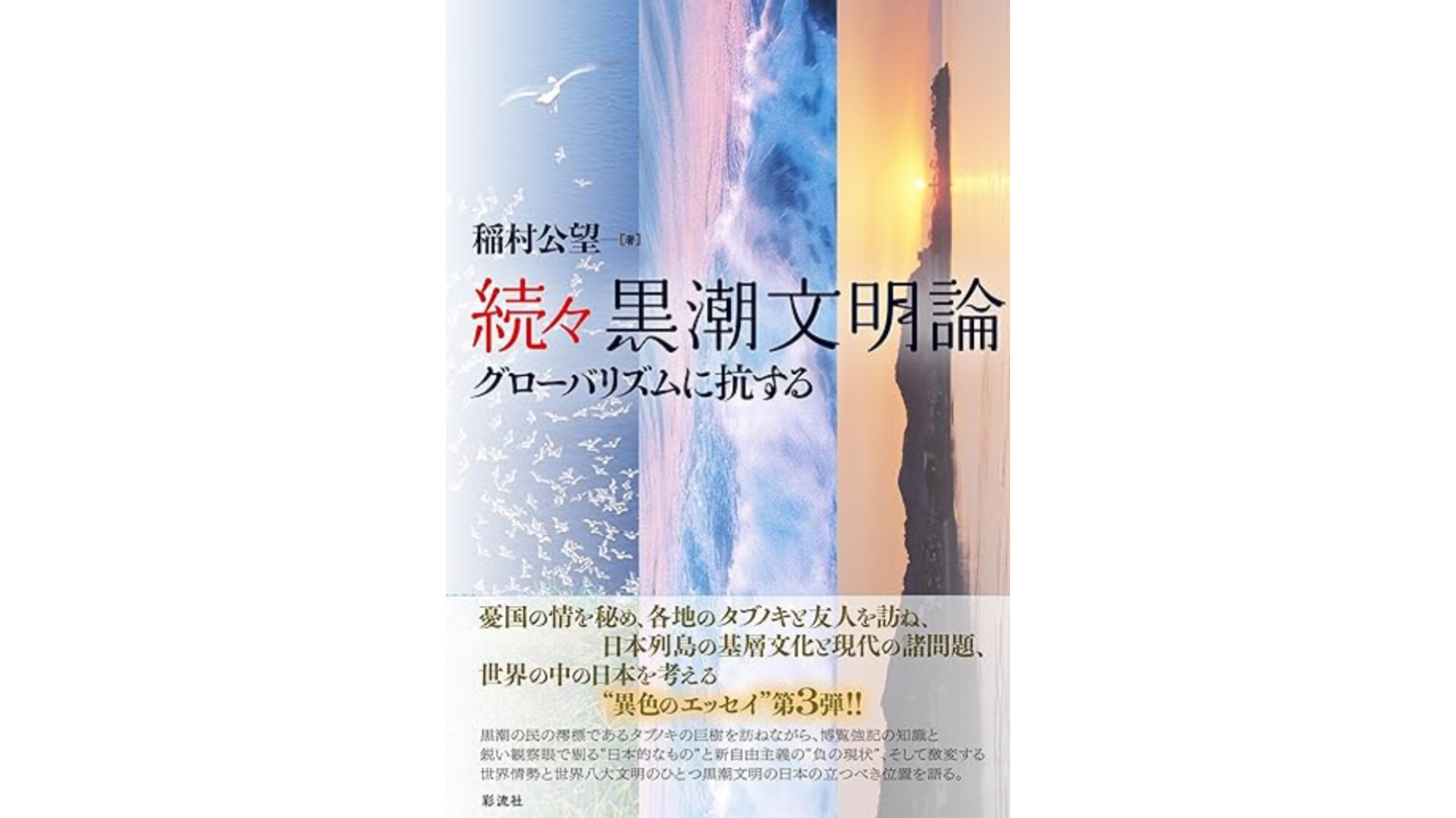
人気記事