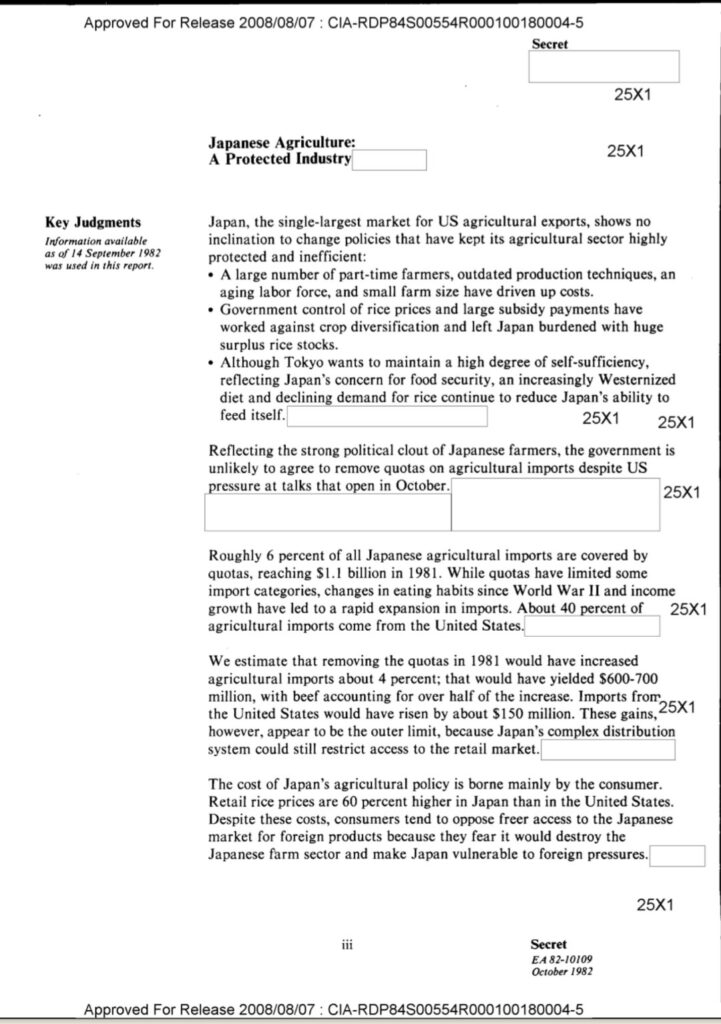
米国農産物輸出の最大市場である日本は、自国の農業部門を高度に保護し非効率な状態に保ってきた政策を変える意向を示していない。
多数の兼業農家、時代遅れの生産技術、労働力の高齢化、農場規模の縮小により、コストが上昇している。
政府による米価統制と多額の補助金支給は作物の多様化を阻害し、日本に膨大な余剰米の在庫を抱えさせることになった。
日本は食糧安全保障への懸念を反映して高い自給率を維持したいと考えているものの、食生活の西洋化と米の需要減少により、日本の食糧自給能力は低下し続けている。
日本農家の強い政治的影響力を反映して、10月に開始される協議で米国からの圧力があったにもかかわらず、政府が農産物輸入割当の撤廃に同意する可能性は低い。
日本の農産物輸入全体の約6%は輸入割当の対象となっており、1981年には11億ドルに達した。輸入割当によって一部の品目が制限されているものの、第二次世界大戦後の食習慣の変化と所得の増加により、輸入量は急増した。農産物輸入の約40%は米国からのものである。
1981年に割当制を撤廃していたと推定すると、農産物輸入は約4%増加し、6億~7億ドルの増収となり、そのうち牛肉が半分以上を占めていたと推定される。米国からの輸入は約1億5000万ドル増加していただろう。しかし、この増加額は上限に過ぎないと思われる。なぜなら、日本の複雑な流通システムが依然として小売市場へのアクセスを制限する可能性があるからだ。
日本の農業政策のコストは主に消費者が負担している。日本の米の小売価格は米国よりも60%も高い。こうしたコストにもかかわらず、消費者は外国製品の日本市場への自由なアクセス拡大に反対する傾向がある。なぜなら、それが日本の農業部門を破壊し、日本を外国からの圧力に対して脆弱にしてしまうことを懸念しているからだ。
関連書籍
原発・正力・CIA: 機密文書で読む昭和裏面史 (新潮新書 249) 新書 – 2008/2/18
有馬 哲夫 (著)
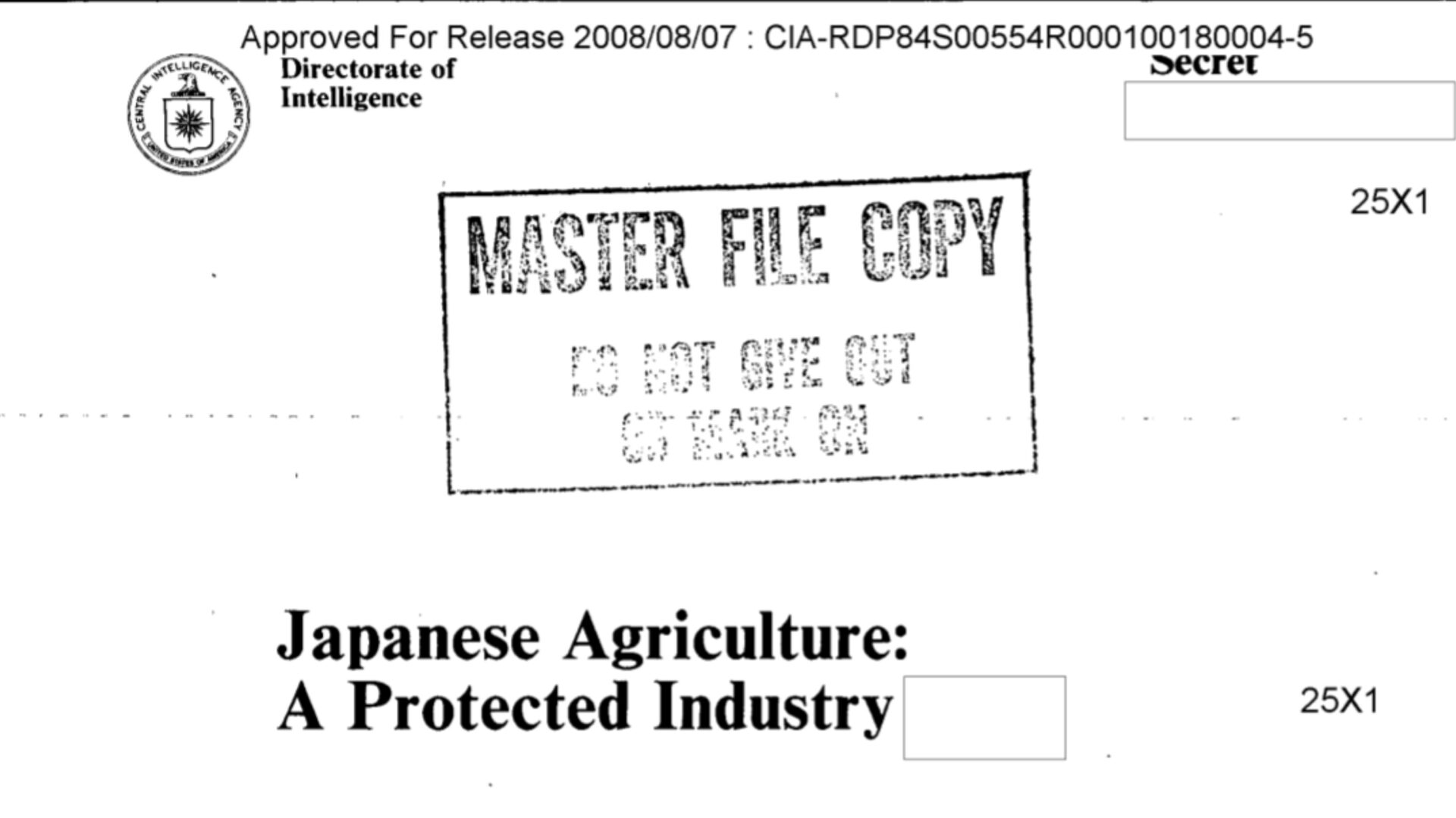
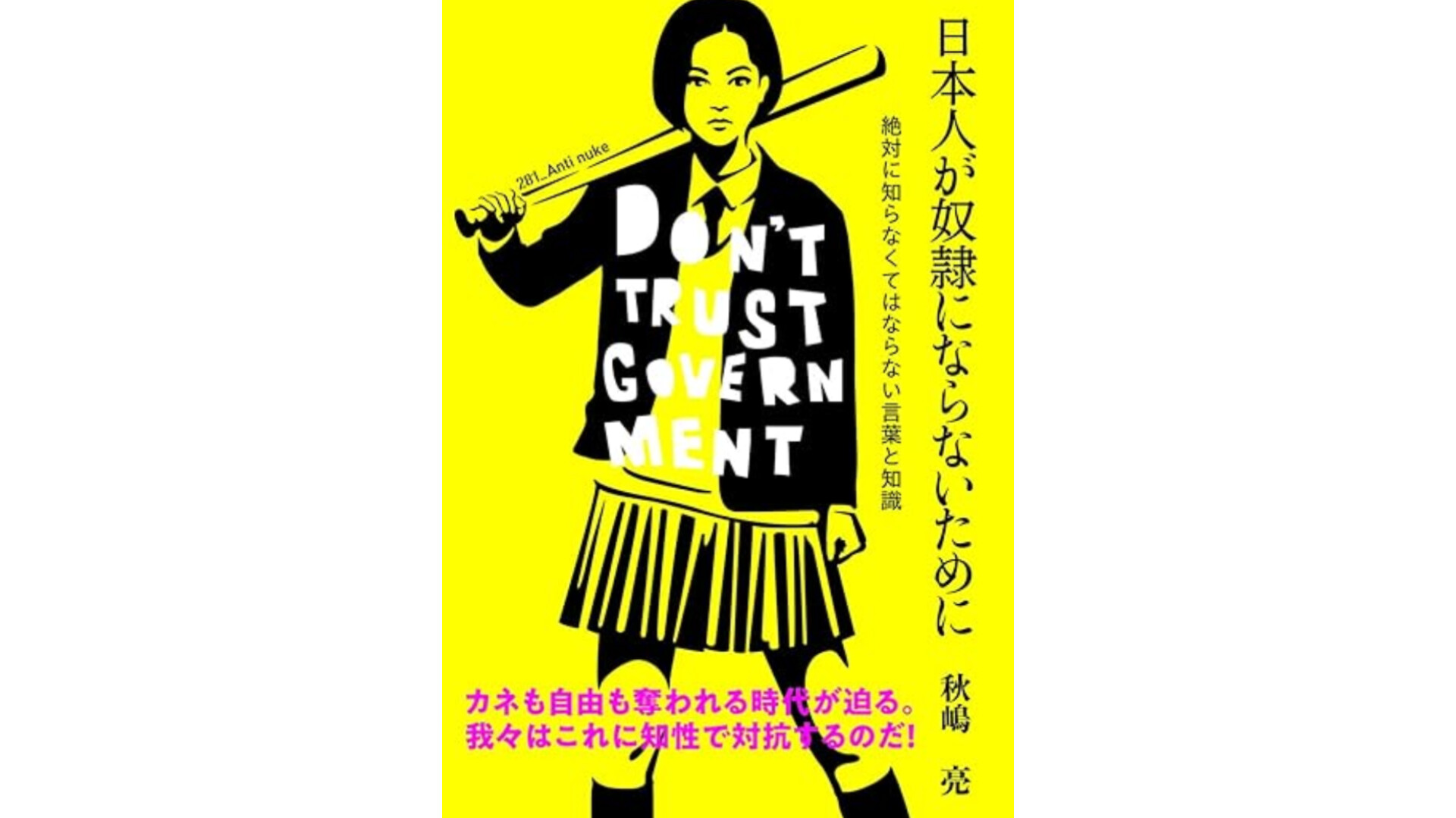

人気記事