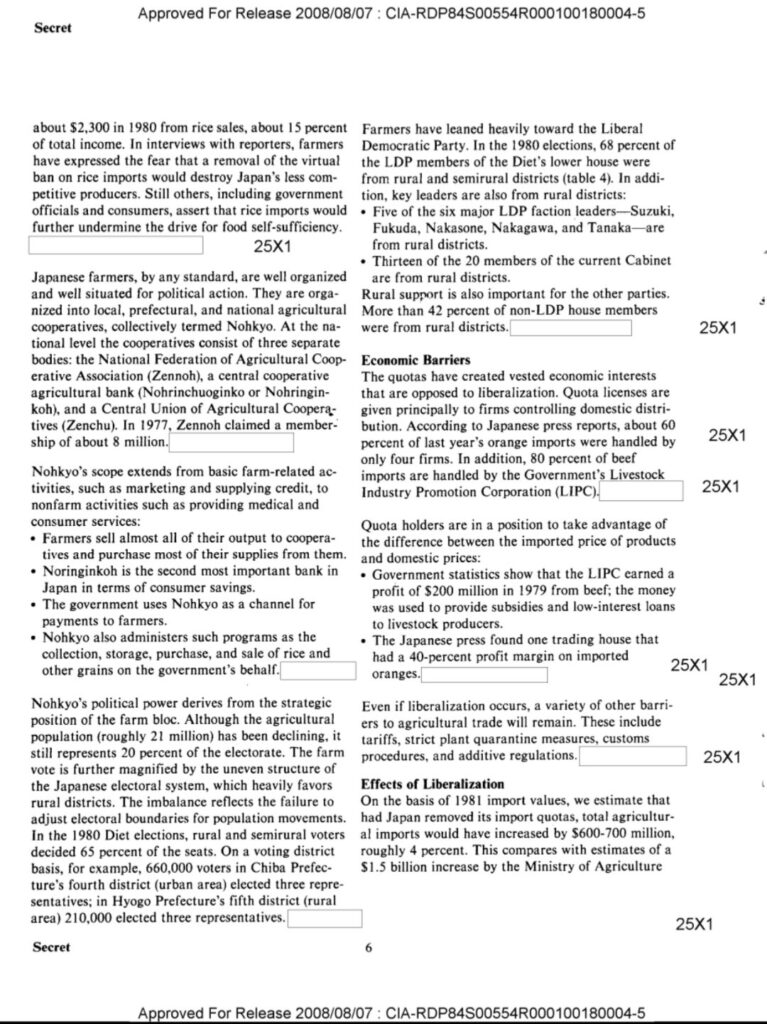
1980年には米の販売による収入は約2,300ドルで、総所得の約15%を占めていました。記者とのインタビューで、農家は米の輸入を事実上禁止していた状態が解除されれば、競争力の低い日本の生産者が破滅するのではないかと懸念を表明しました。一方、政府関係者や消費者を含む一部の人々は、米の輸入は食料自給率の向上をさらに阻害すると主張しています。
日本の農家は、いかなる基準から見ても、組織がしっかりと整っており、政治活動にも有利な立場にあります。彼らは、地域農業協同組合、都道府県農業協同組合、そして全国農業協同組合(総称して農協)に組織化されています。全国レベルでは、農協は全国農業協同組合連合会(全農)、中央農業協同組合銀行(農林中央銀行)、そして全国農業協同組合中央会(全中)の3つの独立した組織で構成されています。1977年、全農は約800万人の組合員数を誇っていました。
農協の活動範囲は、マーケティングや信用供与などの基本的な農業関連の活動から、医療や消費者サービスの提供などの非農業活動にまで及びます。
・農家は生産物のほぼすべてを協同組合に販売し、ほとんどの物資を協同組合から購入しています。
・農林銀行は、消費者貯蓄の面では日本で2番目に大きな銀行です。
・政府は農家への支払い手段として農協を利用している。
・農協はまた、政府に代わって米やその他の穀物の収集、保管、購入、販売などの事業も運営しています。
農協の政治力は、農村地帯の戦略的な立地に由来する。農業人口(約2,100万人)は減少傾向にあるものの、依然として有権者の20%を占めている。日本の選挙制度は不均衡な構造をしており、農村地域に大きく有利なため、農村票の比率はさらに高まっている。この不均衡は、人口移動に合わせて選挙区の境界線を調整できていないことを反映している。1980年の国会選挙では、農村部と準農村部の有権者が議席の65%を占めた。例えば、選挙区ベースで見ると、千葉県第4区(都市部)では66万人の有権者が3人の代表を選出し、兵庫県第5区(農村部)では21万人の有権者が3人の代表を選出した。
農民層は自民党に大きく傾倒している。1980年の衆議院選挙では、自民党議員の68%が農村・準農村地域出身であった(表4)。さらに、主要指導者も農村地域出身である。
・自民党の主要6派閥の指導者のうち、鈴木、福田、中曽根、中川、田中の5派閥は農村地域出身である。
・現内閣の20人の閣僚のうち13人は地方出身者である。
地方からの支持は他党にとっても重要です。自民党以外の下院議員の42%以上が地方出身です。
経済的障壁
割当制は、自由化に反対する既得権益を生み出してきました。割当制の免許は、主に国内流通を支配している企業に与えられます。日本の報道によると、昨年のオレンジ輸入量の約60%はわずか4社によって処理されました。さらに、牛肉の80%は、
輸入は政府の畜産振興公社(LIPC)が担当している。
割当保有者は、製品の輸入価格と国内価格の差を利用できる立場にあります。
・政府統計によれば、LIPC は 1979 年に牛肉で 2 億ドルの利益を上げており、その資金は畜産農家への補助金や低金利融資に充てられた。
・日本の報道機関は、輸入オレンジで40パーセントの利益率を上げている商社があることを発見した。
たとえ自由化が実現したとしても、関税、厳格な植物検疫措置、通関手続き、添加物規制など、農産物貿易には様々な障壁が残るでしょう。
自由化の影響
1981年の輸入額に基づくと、日本が輸入割当を撤廃していた場合、農産物輸入総額は6億~7億ドル、約4%増加していたと推定されます。これは、農林水産省が推定した15億ドルの増加とほぼ同額です。
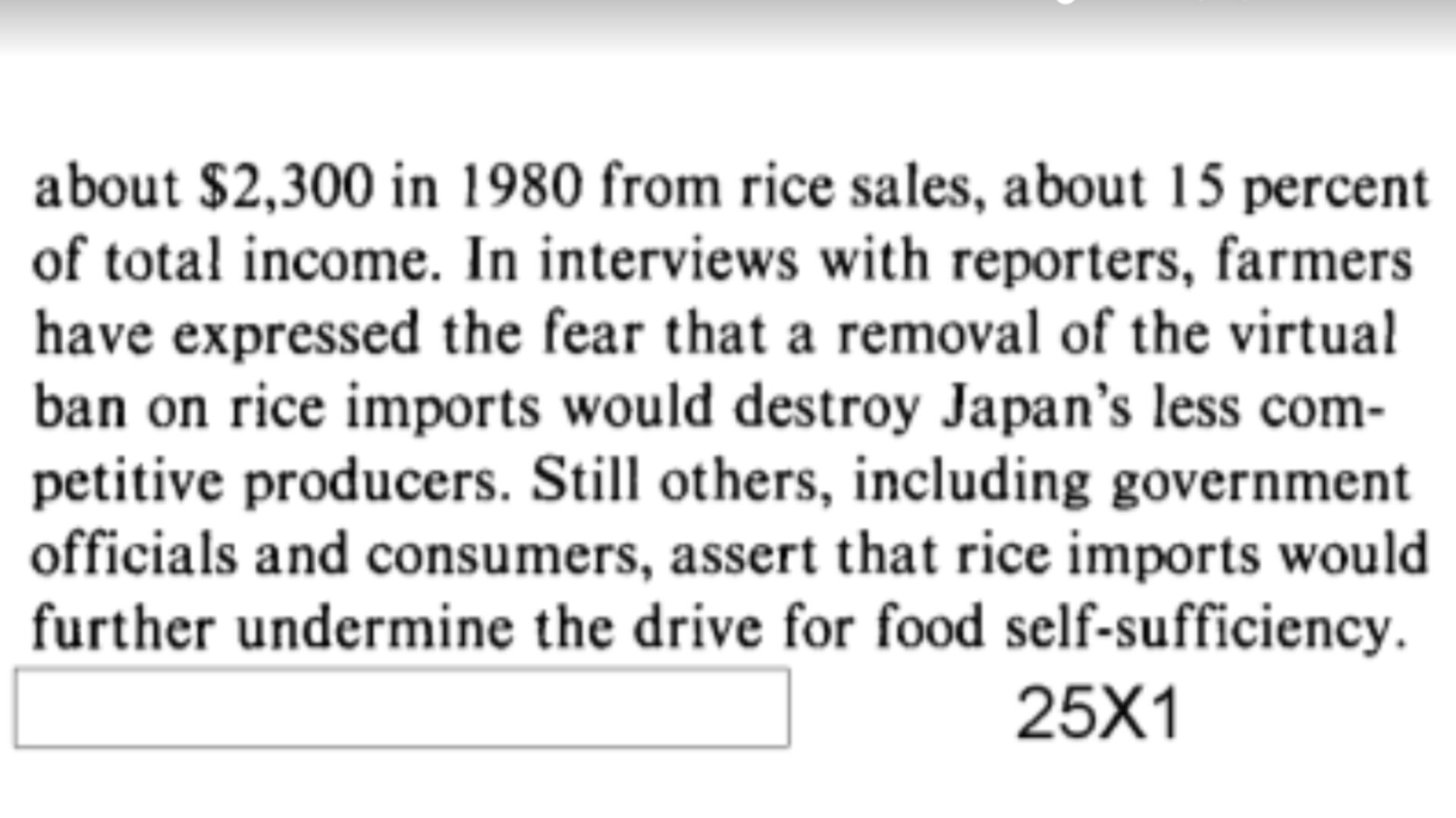

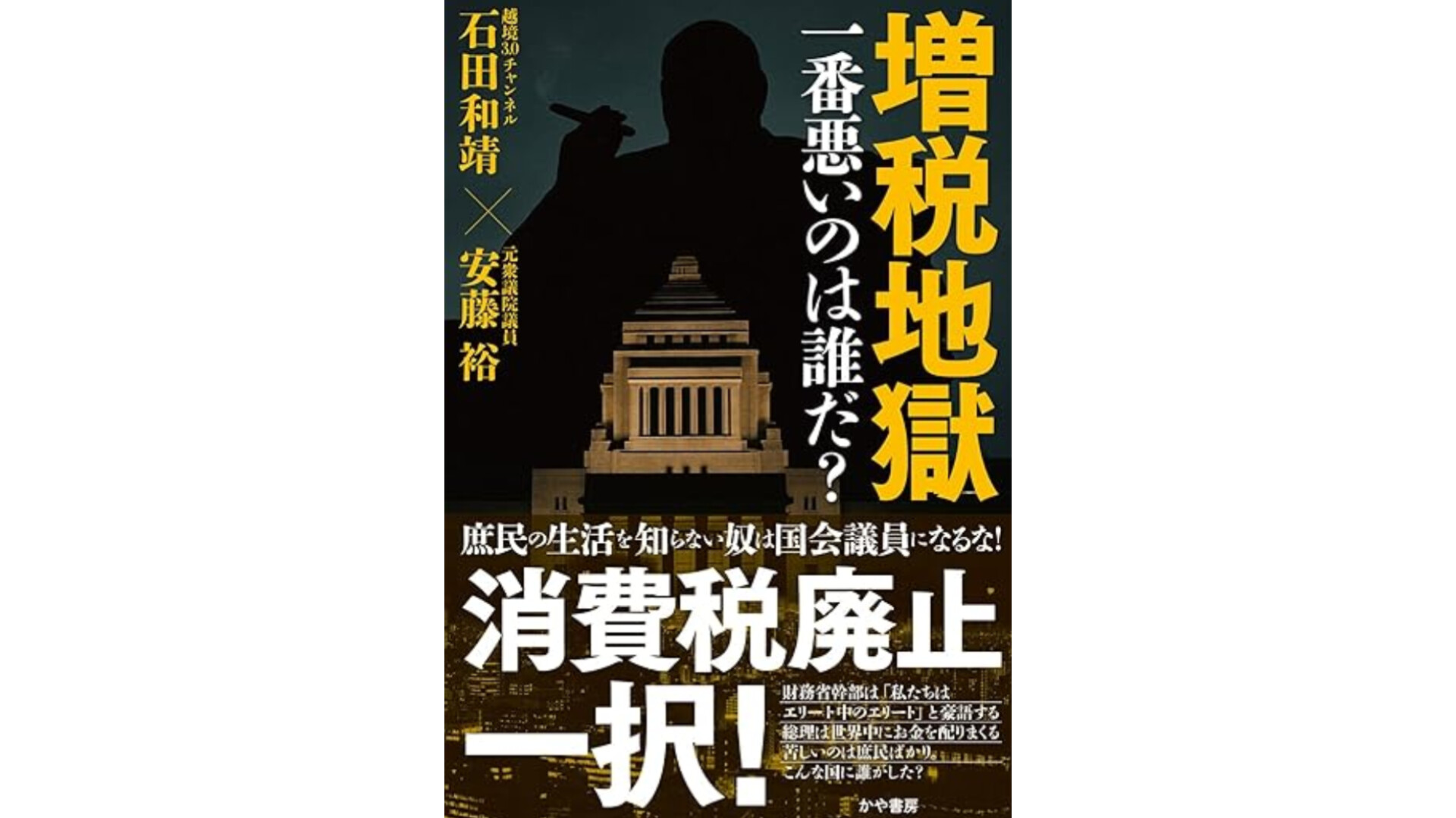
人気記事