認定NPO法人フローレンスは、2017年に東京・渋谷区の待機児童問題の解消を目的として、国と区の補助金を受けて保育施設「おやこ基地シブヤ」を建設しました。この施設は、定員30人の保育所に加え小児科病院も併設されており、地域社会における子育て支援の重要な拠点としての役割を担っています。
しかし、この施設を巡り、フローレンスが開所からわずか2ヶ月後に施設を担保として5,000万円を借り入れていた事実が明らかになりました。さらに、その手続きが行政の承認内容と異なる「違法状態」にあったとの指摘を受け、同法人は公式に謝罪する事態に至りました。プレスリリースでは「公的資金の交付を受けて保育という社会的役割を担う事業者として、このような事態を招きましたことは誠に遺憾であり、深く反省しております」と表明され、公的資金で運営される事業の透明性とコンプライアンスのあり方に深刻な問いを投げかけています。
本稿では、なぜ渋谷区が承認した「抵当権」設定の申請が、最終的に全く性質の異なる「根抵当権」として登記されてしまったのかという核心的な疑問に焦点を当てます。事実関係を整理し、法的な論点を明らかにすることで、この問題の構造を解き明かすことを目的とします。
補助金事業と5,000万円の借入
公的補助金を受けて建設された施設は、その性質上、財産処分に関して厳しい制約が課せられます。これは、税金を原資とする公的資金が、交付目的から逸脱して使用されることを防ぐための重要なガバナンス上の原則です。補助金交付の対象となった不動産を担保提供するなどの行為は、原則として禁止されており、例外的に承認を得る場合でも、その使途は厳格に管理されなければなりません。
本件の背景にある事実関係は、以下の通り整理されます。
• 施設名: 保育施設「おやこ基地シブヤ」
• 所有者: 認定NPO法人フローレンス
• 建設年: 2017年
• 建設目的: 渋谷区の待機児童問題の解消
• 資金源: 国と渋谷区からの補助金
• 借入: 開所から2ヶ月後、銀行から5000万円を借入
フローレンスの赤坂緑代表理事によれば、借り入れた5,000万円の使途は、「ほとんどが建物の建設のために事業負担分として支払う部分に使っている」ほか、一部は「保育園を開設するために事前に人を採用して、育成しておく」ための人件費などに充てられたと説明されています。これらの使途は一見、事業目的に関連しているように見えますが、問題の本質は、その資金調達のために選択された法的な手段が不適切であった点にあります。誤った担保権の設定は、将来的な資金の目的外使用への扉を開きかねないガバナンス上の重大なリスクを生じさせました。
「抵当権」と「根抵当権」の決定的な違い
NPO、特に公的資金の交付を受ける団体にとって、担保権の種類を正確に理解し、適切に運用することは、ガバナンスとコンプライアンスの根幹に関わる重要な要素です。「抵当権」と「根抵当権」は、名称こそ似ていますが、その法的な性質と経済的な機能は全く異なります。この違いを理解することが、本件の問題性を把握する上での鍵となります。
渋谷区保育課の金城哲也課長の説明に基づき、両者の違いを比較すると以下のようになります。
| 比較項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
| 資金の使途 | 特定の債務に紐づき、本件では保育事業に限定される。 | 資金使途の制約が緩く、不動産関連以外の事業目的にも利用可能。 |
| 借入の柔軟性 | 一度の借入と返済で担保権は消滅する。 | 極度額の範囲内であれば、何度でも借入と返済を繰り返せる。 |
金城課長が指摘するように、「根抵当権」は「不動産の価値の上限額まで借りたり返したりを何回もできる」上に、「不動産以外の事業目的としても借り入れができる」という性質を持つため、補助金事業の対象施設に設定することは「大きな問題」とされています。つまり、補助金の目的外使用につながるリスクが極めて高い担保権なのです。
これら二つの担保権の性質の違いを理解した上で、次に、実際の手続きにおいて何が申請され、何が登記されたのか、その食い違いを見ていきます。
渋谷区の「承認」と実際の「登記」
行政手続きにおいて、申請内容と承認内容、そして最終的な実行内容が一致することは、行政と事業者の間の信頼関係の基礎をなすものです。この一貫性が崩れるとき、手続きの正当性そのものが揺らぎ、監督責任の所在も曖昧になります。本件では、まさにこの「手続きの不一致」が問題の核心にあります。
事案の経緯を時系列で分析すると、深刻な矛盾が浮かび上がります。
1. フローレンスの申請: フローレンスは渋谷区に対し、「抵当権」を設定したいとの申し出を行いました。
2. 渋谷区の承認: 渋谷区は、この申し出を受け、「抵当権」の設定を正式に承認しました。
3. 実際の結果: しかし、実際に法務局で登記されたのは、承認内容とは異なる「根抵当権」でした。
この状況は、単なる事務的なミスでは済まされません。新日本パートナーズ法律事務所の池田康太郎弁護士は、「補助金で作った建物の処分とかも含めて、一律禁止されている」と前置きした上で、次のように指摘しています。
「今回『抵当権』で承諾を得たにもかかわらず『根抵当権』をつけているというのは、違法状態にあるということ」
弁護士が「違法状態」と断言するように、行政から得た承認の範囲を逸脱した行為は、法的な正当性を欠くものです。この重大な不一致に対し、関係各所の対応と説明責任が問われています。
関係者の対応と現在の状況
問題が発覚した後の組織の対応は、その透明性、説明責任、そして信頼回復への真摯な姿勢を測る上で極めて重要です。本件に関わるフローレンスと渋谷区は、それぞれ原因究明と是正措置に乗り出しています。
フローレンス側の対応は、主に以下の3点に要約されます。
• 認識に関する説明: 赤坂緑代表理事は、「『根抵当権』と『抵当権』が全く性質の異なる物であるということを十分に理解していなかったという認識でおります」と述べ、法的な認識の不足があったことを認めました。
• 是正措置: 既に、借り入れた5,000万円を金融機関に一括返済する手続きを開始しており、その上で登記された根抵当権を抹消する手続きを進めていると説明しています。
• 内部調査: なぜこのような事態が発生したのか、2017年当時の担当者に聞き取り調査を進めています。赤坂氏は「本当に組織の至らなかったところだと思う」と述べ、組織的な不備であったと反省の意を示しました。
一方、監督官庁である渋谷区も、フローレンスから「抵当権」の申請を受け承認したにもかかわらず、なぜ「根抵当権」が登記されたのか、2017年当時の担当者に聞き取りを行い、原因究明を進めている状況です。
両者が調査を進める中で、依然として手続きのプロセスにおける具体的な経緯は不明なままであり、核心的な疑問は残されています。
残された疑問と公的資金の透明性
本件を巡る調査が進む中で、最も核心的な疑問は依然として解明されていません。それは、「なぜ事業者からの『抵当権』の申請が、行政の承認を経て、最終的に『根抵当権』として登記されたのか」という点です。単純な認識不足という説明だけでは、申請、承認、登記という複数のチェックポイントをこの食い違いがすり抜けてしまった理由を完全に説明することは困難です。
この事案は、単なる一NPOの事務的な過誤という問題に留まらず、より広範な構造的な論点を提起しています。
• NPOのガバナンス体制: フローレンス側が「十分に理解していなかった」と説明したことは、公的資金という社会の共有財産を扱う団体に求められるべき、内部の法務・コンプライアンス体制の決定的な欠陥を浮き彫りにしています。
• 行政の監督責任: 補助金を交付した後の事業監督や、財産処分等に関する承認手続きにおける確認プロセスの実効性が問われています。承認した内容と異なる登記がなされた事実を長期間見過ごしていたことは、監督官庁としての責任を免れません。
• 手続きの透明性: 申請者の「認識不足」が、なぜNPOの内部プロセス、融資を実行した金融機関の法務審査、そして行政の監督という複数のチェック機能をすり抜けてしまったのか。これは手続き全体の透明性と、関係機関相互のチェック機能に構造的な課題がある可能性を示唆しています。
フローレンスと渋谷区双方による調査結果の公表が待たれます。この事案の全容解明は、今後のNPOと行政の健全なパートナーシップを築き、公的資金の使途における透明性を確保していく上で、極めて重要な教訓となるはずです。

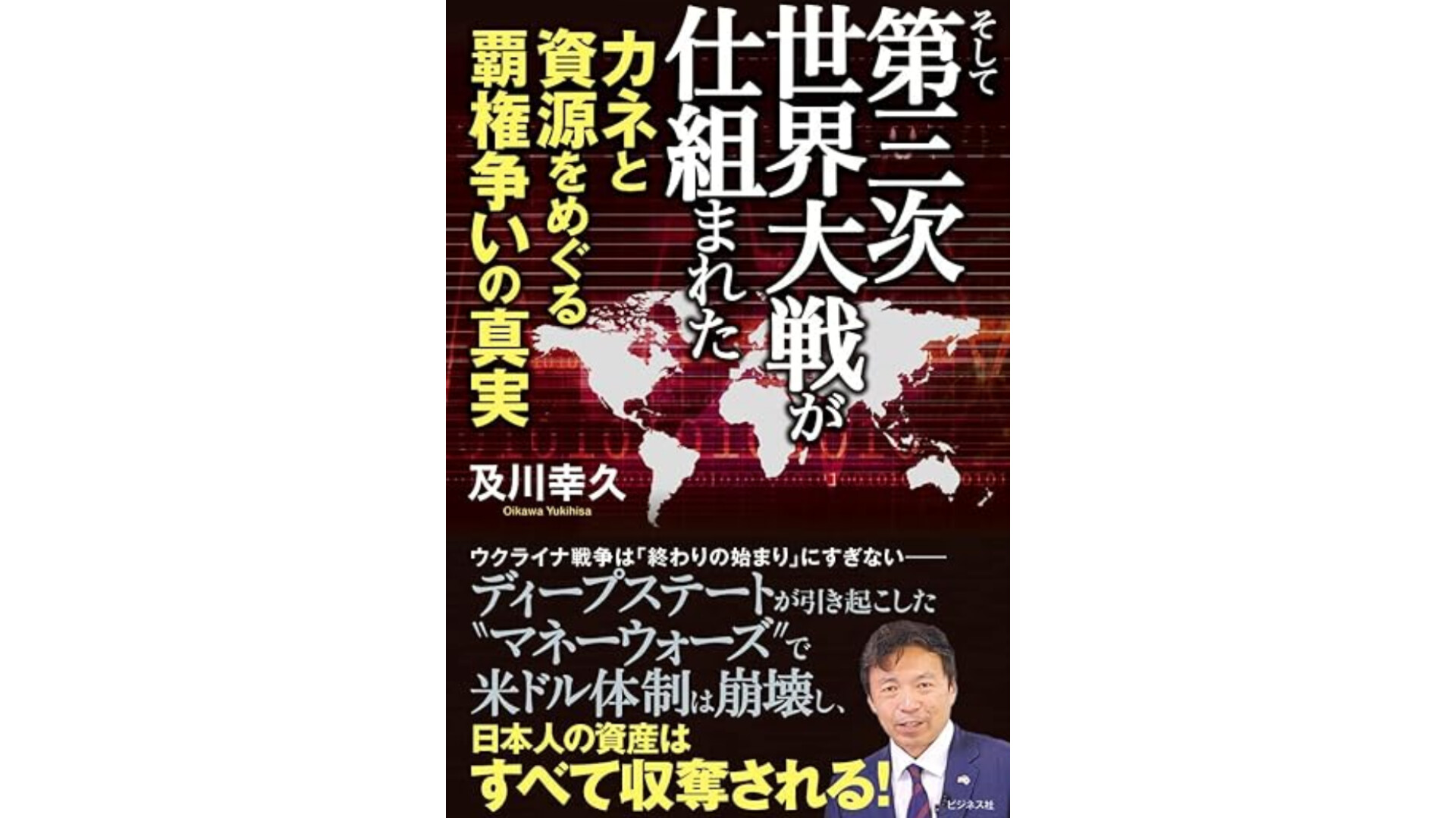
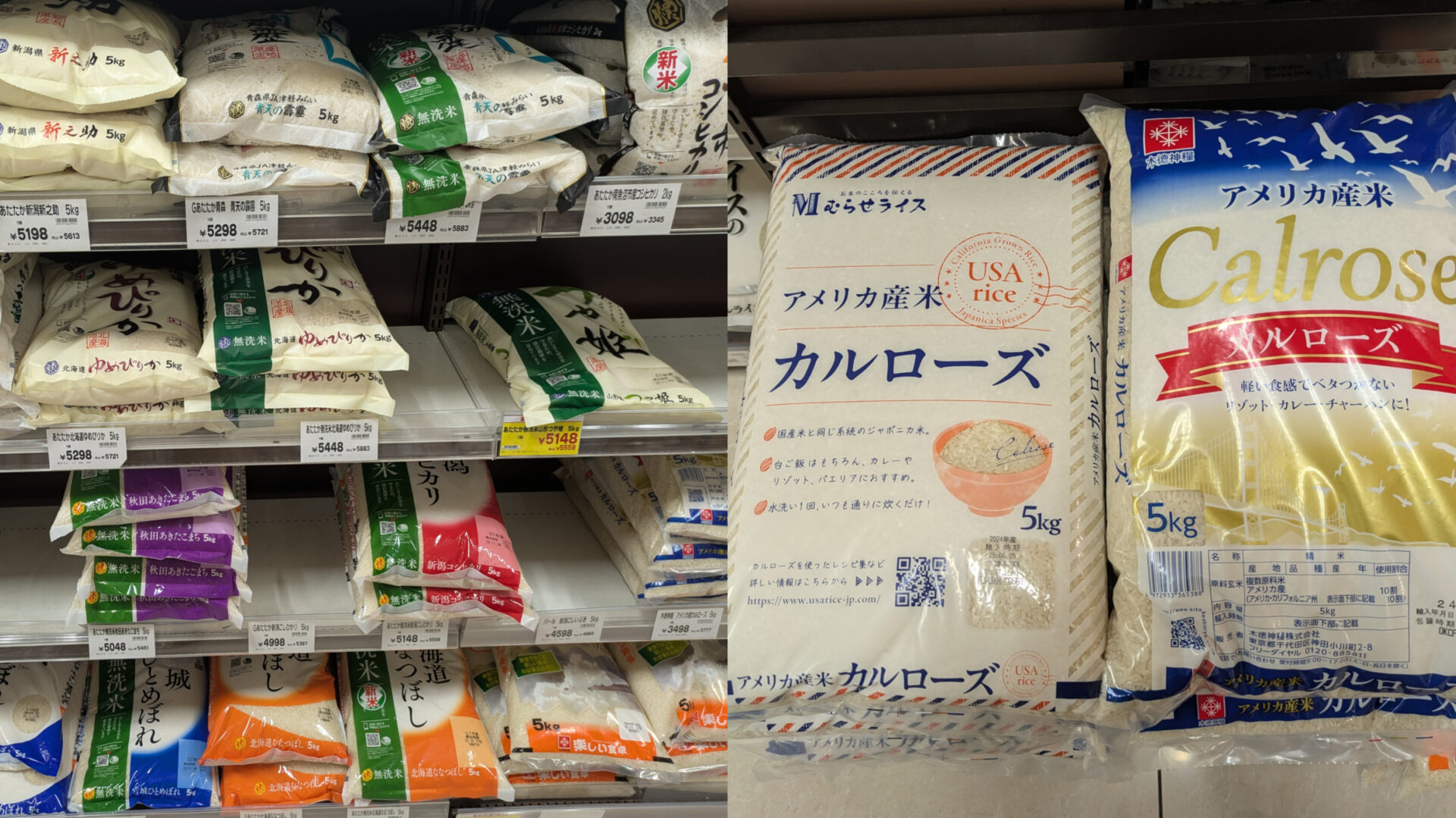
人気記事