5年前の2020〜2021年、コロナ禍の不安がピークに達した時期、政府の権限を強めるための憲法改正、特に「緊急事態条項」の新設を求める声がニュースを賑わせました。あの頃、それが私たちの生活と具体的にどう関係するのか、いまひとつ分かりにくいと感じていた人も多かったのではないでしょうか。
しかし、憲法学者の石川健治氏の解説によれば、この議論には私たちの自由や社会のあり方を根本から変えてしまうかもしれない、非常に重要な論点が隠されていました。この記事では、石川氏の分析をもとに、あのコロナ禍における憲法議論の核心を5つのポイントに分けて、当時を振り返りながら分かりやすく解き明かしていきます。
「緊急事態」には2種類ある:事実で判断する「客観的」なものと、権力者が決める「主観的」なもの
あの時期の憲法改正論議を振り返る上で最も重要な鍵は、「緊急事態」の捉え方には根本的に異なる2つの種類があったことを知ることです。石川氏はこれを「客観的な緊急事態法」と「主観的な緊急事態法」として区別していました。
- 客観的な緊急事態法
これは、科学的根拠や客観的な事実に基づいて「本当に緊急事態なのか」を判断する考え方です。例えば、感染症の拡大のような状況で、「生命を守る」ことと「経済を回す」こと、どちらも正当な利益が衝突する場面で、政府は苦渋の決断を迫られました。この仕組みは、そうした難しい選択が、後から裁判所などの第三者によって「少なくとも違法ではなかった」と判断され、正当化されるためのものです。判断の根拠が客観的な事実にあるため、事後的な検証が可能になります。 - 主観的な緊急事態法
一方、こちらは「何をすべきか」ではなく、「誰が緊急事態だと決めるのか」という点に集約されます。この考え方は、ナポレオンが欧州を席巻した後の王政復古期に生まれました。当時の王政は、立憲主義に縛られない憲法を作る意図のもと、緊急事態の判断基準を「何が危機か」という客観的な問いから、「誰が危機だと決める権力を持つのか」という主観的な問いへとすり替えたのです。国王や大統領といった特定の権力者が「今は緊急事態だ」と宣言すれば、その判断が絶対となり、事後的にその是非を問うことができなくなります。判断の根拠は権力者の主観にあるため、第三者によるチェック機能が働きません。
あの憲法改正論議で語られた「緊急事態条項」は、後者の「主観的」な仕組みに近いものでした。この重要な区別をまず念頭に置かないとなりません。本来は客観的であるべき危機対応の議論が、いかに危険な方向へと「横滑り」してしまったのかが、当時を振り返るうえで極めて重要だからです。
議論はすり替わる:「何をすべきか」から「誰が決めるのか」という危険な横滑り
コロナ対策のような危機対応は、本来、科学的根拠に基づく「客観的」な議論であるべきでした。しかし石川氏は、こうした議論が「誰が決めるのか」という権力者の問題へと「横滑り」してしまった危険性を、当時から指摘していました。
例えば、本来は「どのような対策が最も効果的か」を科学的に議論すべきなのに、いつの間にか「都知事と総理大臣のどちらが主導権を握るのか」といった権力争いの側面がクローズアップされてしまった現象がそれに当たります。この「横滑り」が起きると、本当に必要な対策よりも、政治的なパフォーマンスや決断の先陣争いが優先されかねません。
結果、客観的な状況分析が軽んじられ、効果の薄い対策や根拠のない判断がまかり通ってしまう危険性が高まりました。石川氏が紹介したある政治哲学者の言葉は、この問題の本質を鋭く突いています。
私の友人の政治哲学者の言い方で言いますと、海図と羅針盤をしっかり確保するということであって、この船長にすべてを任せてしまうということではないはずです。
重要なのは、客観的な情報(海図と羅針盤)を確保することであり、特定のリーダー(船長)に全ての判断を丸投げすることではないのです。あの頃の議論を振り返ると、この視点がどれほど欠けていたかがわかります。
「緊急事態条項があれば解決する」という幻想:ウイルスは忖度しない
憲法改正を主張する人々が求めた「緊急事態条項」は、本質的に「主観的な緊急事態法」、つまり「特定のリーダーが全てを決める」仕組みの導入を目指すものでした。
しかし石川氏は、あの1年間のコロナ禍の経験こそが、「誰か一人のリーダーに強大な権限を与えれば問題が解決する」という考えが幻想であることを逆説的に証明した、と指摘していました。世界を見渡しても、トランプ前大統領のように強権的なリーダーシップを掲げた指導者が、必ずしもコロナ対策で正しい判断を下したわけではありませんでした。
石川氏が指摘するように、トランプ氏はコロナ禍で退陣し、日本の安倍政権もまた倒れました。むしろ、客観的な科学的知見を軽視したことで、事態を悪化させた例も見られます。緊急事態条項を新設しても、ウイルスという客観的な危機そのものには何の影響も与えません。むしろ、権力者が下した誤った判断を「緊急事態だから」という理由で正当化し、誰も責任を問えなくしてしまう危険性すらあります。
石川氏が指摘するように、「忖度しないコロナウイルス」の前では、客観的な事実に基づかない主観的な判断は無力だったのです。あの経験を振り返る今、この教訓はより鮮明です。
問題は「権限の弱さ」ではなく「信頼の喪失」:なぜ政府の要請は響かなくなったのか
「欧米に比べて日本の規制は緩すぎる。もっと強制力のある権限を政府に与えるべきだ」という議論が、当時ありました。しかし石川氏は、その前提にこそ問題があると分析していました。あの1年で政府の自粛要請などの効果が薄れてきた本質的な理由は、法的な権限の弱さにあるのではありません。
むしろ、政府自身が「ブレーキを踏むのかアクセルを踏むのか」といった矛盾したメッセージを発信し続け、一方で政治家や官僚の会食問題などが発覚したことで、国民の「信頼」が失われたことにあるのです。
また、安易に海外の事例を当てはめることにも注意が必要です。欧米社会では、個人の利益が優先されるため、全体の利益のための規制には強制力が必要となる前提があります。一方、日本の現行法は、強制によらずとも市民社会の協力と連帯によって危機を乗り越える、という考え方を前提に立っています。
権限を強化して人々を強制的に従わせる社会を目指すのか、それとも信頼を再構築して市民の自発的な協力を促す社会を目指すのか。石川氏は、権限強化を議論する前に、まず政府が揺るぎない正しいメッセージを発信し、国民の信頼を回復することが先決だと主張していました。あの頃の信頼喪失を振り返ると、この指摘の重みが実感されます。
「分かりやすさ」の罠:なぜ複雑で分かりにくい仕組みに価値があるのか
危機的な状況にあるとき、私たちは「すべてを決めてくれる強いリーダー」や「問答無用で実行される分かりやすい解決策」に魅力を感じてしまいがちでした。しかし石川氏は、その「分かりやすさ」にこそ、立憲主義を脅かす罠が潜んでいると、当時から警告していました。石川氏によれば、「専制主義の権力」と「立憲主義の権力」には本質的な違いがあります。
- 専制権力: その特徴は「問答無用」で「説明をしない」ことです。一直線で段階が少ないため、非常に「分かりやすい」権力と言えます。
- 立憲主義の権力: 常に憲法に基づいて自らの正当性を「説明し、正当化する」ことを求められます。手続きが「多段階的」で複雑なため、一見すると「分かりにくい(ややこしい)」権力です。
危機において人々が専制的な「分かりやすさ」に惹かれるのは自然な心理かもしれません。しかし、立憲主義が持つ一見非効率な「ややこしさ」や多段階的な「ブレーキ」にこそ、権力の暴走を防ぎ、取り返しのつかない事態を避けるための重要な価値があるのです。
わかりやすい話っていうのは一直線の議論ってことなんですよね。…専制権力っていうのはわかりやすい権力なんですよ…立憲主義的な権力っていうのは、そうしないように多段階的にできている。多段階的に出来てるってことは、まあある意味わかりにくいということでもあるわけですよ。ややこしい。だからまあわかりやすい話が良いことだという側面ももちろんあるんですけれども、しかしわかりにくいこと、あるいはそのややこしいことに意味があるかもしれないという風にも考えてみていただきたい。
コロナ禍という未曾有の危機に乗じて、安易で「分かりやすい」解決策に飛びついたあの議論には、大きな危険が伴っていました。一度強化された権力や、一度手放してしまった自由は、危機が去った後に元に戻すのが非常に難しいからです。
5年経った今、私たちは、目の前の不安を解消するために、将来にわたって私たちの自由を縛るかもしれない「後遺症」を残してしまってはいけません。あのコロナ禍を振り返り、今こそ、冷静に議論の本質を見極めることが求められています。
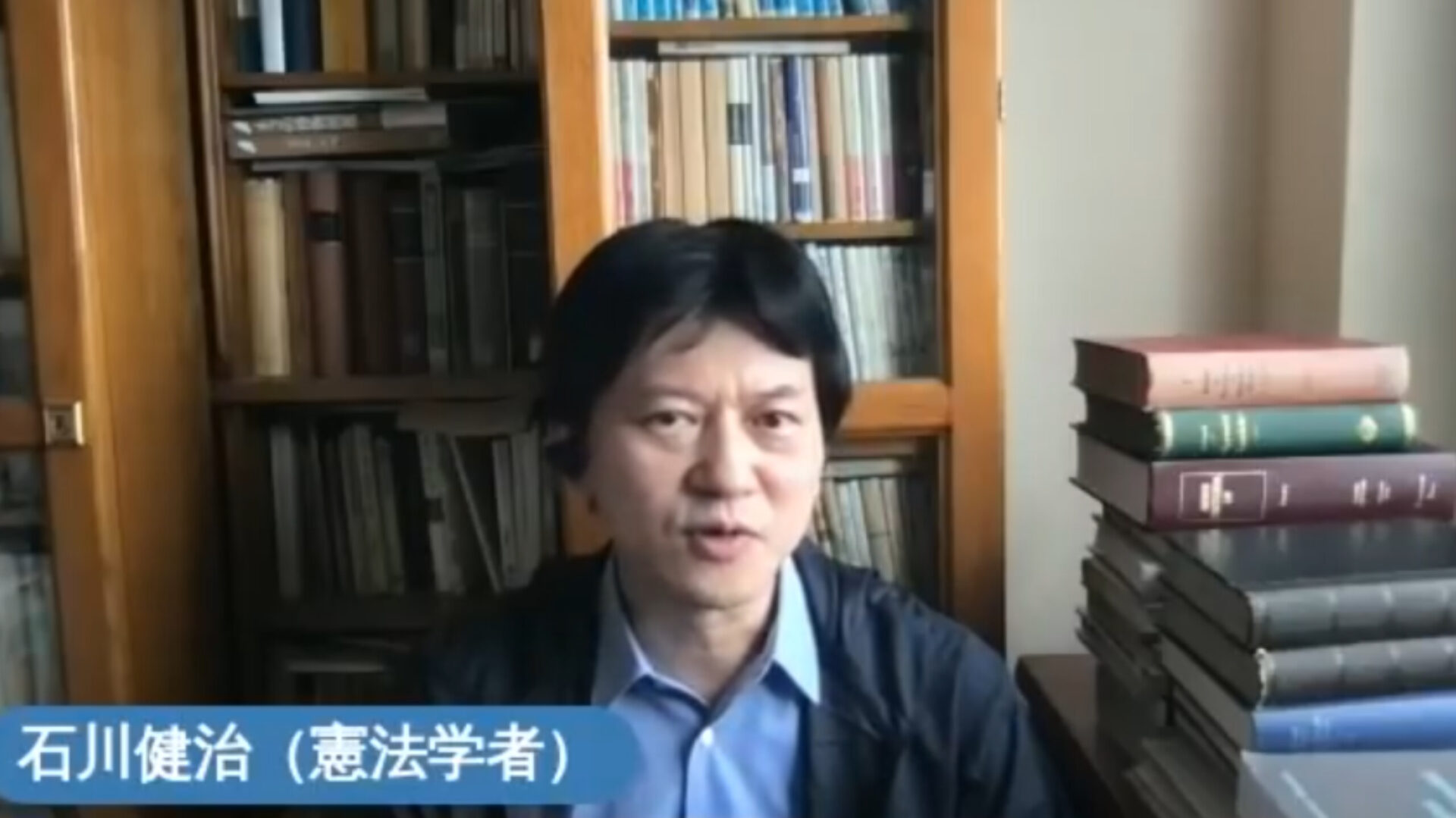

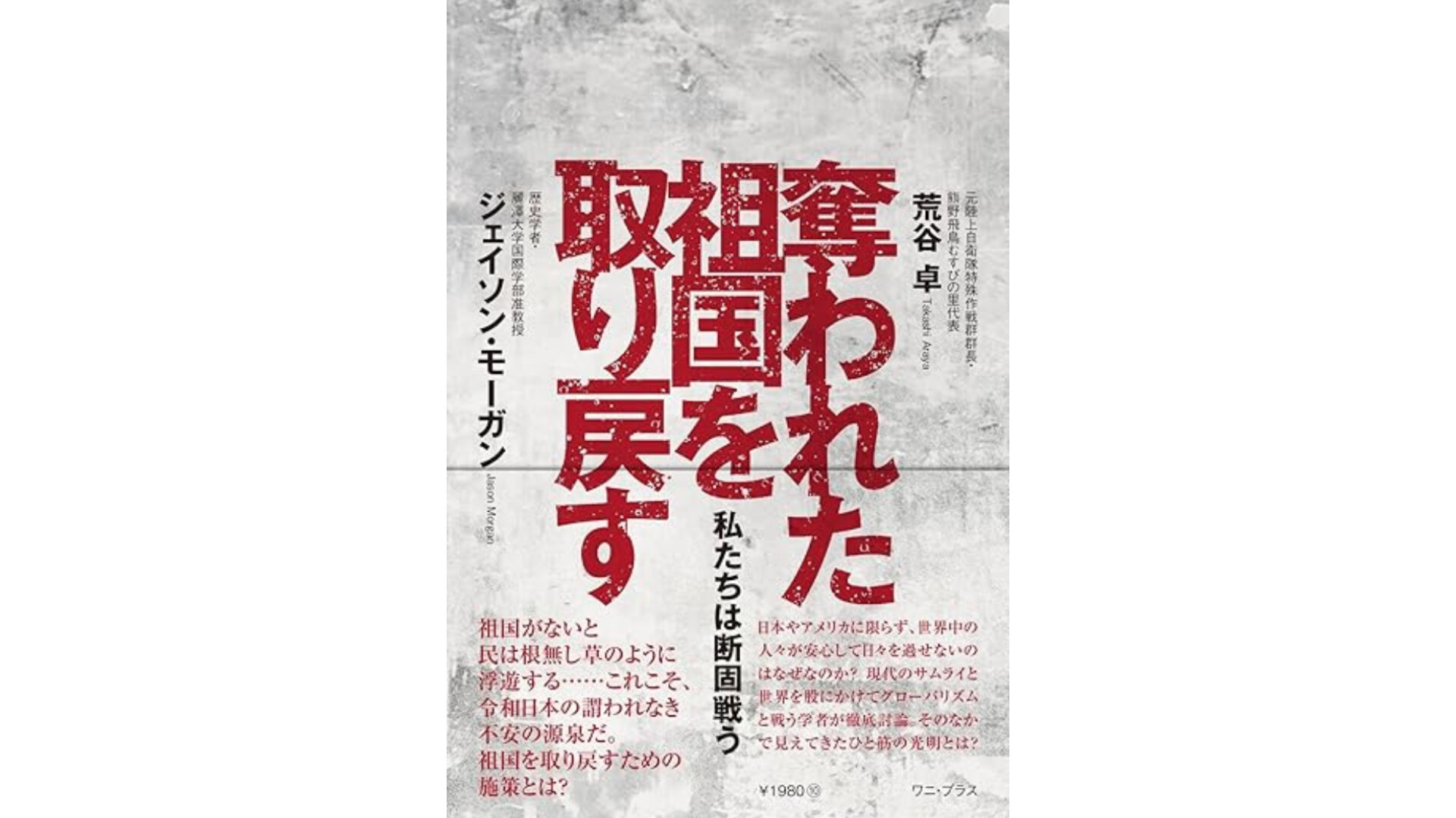
人気記事