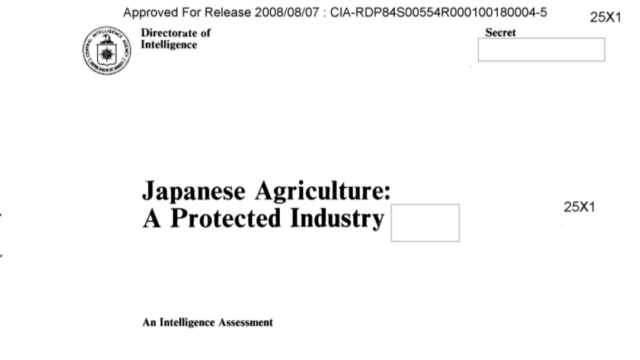 健康
健康 CIA機密解除文書「当初は緊縮財政を約束していましたが、日本政府は今年、農家からの圧力に屈し、生産者価格を1.1%引き上げました。」『日本の農業:保護された産業(1982年10月)』連載4
土地の賃貸、長期低利融資、そして補助金。農家所得の安定化を図るため、東京は米価の国家統制を実施し、大豆の栽培に補助金を支給した。農家所得の安定化には成功したものの、農家規模がほとんど変わらなかったため、農業生産性の向上には至らなかった。・米...
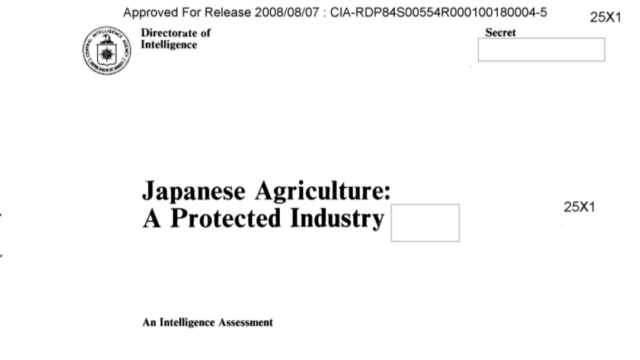 健康
健康  健康
健康  社会
社会