建築家・丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体費用を巡る住民監査請求が、11月5日付で棄却されました。この決定は、単なる行政手続きの一つの完了を意味するものではありません。
この「棄却」という結論の背景に潜む、行政の説明責任の欠如と市民参加の形骸化という深刻な問題を深く掘り下げます。文化的に極めて重要な建築物の運命が、具体的な対案を顧みられることなく、行政の一方的な判断によって決定されようとしています。この現状は、地方自治における透明性と熟議のプロセスそのものに、根本的な問いを投げかけています。
この決定がもたらす影響は、単に一つの建築物が失われるという事実に留まりません。それは、行政の意思決定プロセスに対する市民の信頼を揺るがし、今後の公共資産のあり方に永続的な影を落とす可能性があります。この問題の核心にある、住民側が提示した具体的な「再生案」と、県の揺るぎない「解体決定」との間の決定的な溝について詳しくお伝えします。
対立の核心:住民による「再生案」と県の「解体決定」
今回の住民監査請求が注目されるべき点は、それが単なる解体への反対運動ではなく、具体的な対案を伴うものであったという事実です。再生を目指す市民団体と、解体を既定路線とする香川県。両者の間にある根本的な認識の隔たりを理解することが、この問題の本質を解き明かす鍵となります。
市民側は「公費不要の再生」という可能性を提示したのに対し、県側は一貫してその道を閉ざしてきました。「旧香川県立体育館再生委員会」の主張請求者である「旧香川県立体育館再生委員会」の長田慶太委員長は、県の解体方針における正当性の欠如を指摘し、主に以下の3つの論点を掲げて解体費用の支出差し止めを求めました。
- 公費不要の再生案の無視: 県が、委員会が提案した民間による買い取りなど公費を使わない再生案について、協議や検討を行っていないこと。
- 安全性の根拠の欠如: 県が下した建物の安全性に関する判断が、技術的な裏付けを欠いていること。
- 不透明な解体費用: 県が算定した8億4,700万円という解体費用が、市場の相場と比較して著しく高額であること。
これらの主張は、県が代替案を真摯に評価する責務を放棄し、不十分な根拠と不透明な費用算定に基づいて解体方針を強行しているという、手続き的・内容的な正当性の欠如を鋭く指摘するものでした。しかし、県の監査委員はこれらの具体的な指摘にどう向き合ったのでしょうか。
監査委員による「棄却」理由の批判的検証
県の監査委員が下した「棄却」という判断は、市民側の主張を退ける形となりました。しかし、その判断理由を詳細に分析すると、論点を正面から受け止めるのではなく、行政の裁量を追認する姿勢が色濃く浮かび上がってきます。市民の異議申し立てを検証する最後の砦であるべき監査制度が、十分に機能したとは言い難いです。
曖昧な「総合的考慮」という論理
監査委員が請求を棄却した最大の理由は、「県は建物の安全性や利活用の可能性、文化的価値などの事情を総合的に考慮した上で解体を決定した」ものであり、「その判断が著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱、濫用したものとは言えない」というものでした。
しかし、この「総合的に考慮した」という言葉は、具体的な論点を回避するために行政が多用する、典型的な官僚的答弁です。再生委員会が提示した個別の論点に直接反論することなく、包括的な表現の裏に判断を隠すための、使い古された行政の盾に他なりません。
これでは、なぜ再生案が検討に値しないのか、なぜこの費用が妥当なのかという住民の最も知りたい問いに何一つ答えていません。
透明性の欠如を認めながらの容認
興味深いことに、監査委員は県のプロセスに問題があったことを部分的に認めています。
民間の利活用策を募ったサウンディング型市場調査について、「実現可能性の精査や検討結果が公表されていないことは透明性確保の観点から必ずしも十分なものとは言えない」と、手続き上の不備を明確に指摘しました。
ところが、その直後に「調査の実効性が極めて乏しいものとまでは言えない」と結論付けています。これは明らかな論理の飛躍です。「十分ではない」と監査委員自らが認めたプロセスが、なぜ最終的に容認されるのか。この矛盾は、行政側の手続きを結論ありきで追認する姿勢の表れと言わざるを得ません。
高額な解体費用の不問
解体費用が著しく高額であるという住民の主張に対しても、監査委員の検証は踏み込みを欠きました。委員は「建物の形態や規模、工事の特殊要因などから相場や他の施設との単純な比較は難しい」と結論付けました。
これは、費用の妥当性を検証する責任を事実上放棄し、県の算定を無条件に受け入れる結果につながっています。特殊要因があるのであれば、その内容を具体的に精査し、費用の正当性を市民に説明することこそが監査に求められる役割のはずです。
これら三つの論点は、個別の瑕疵ではなく、相互に連関し、行政の不作為を正当化する構造を形成しています。すなわち、曖昧な「総合的考慮」という言葉を盾に「透明性の欠如」を不問に付し、その結果として「高額な解体費用」の妥当性検証が放棄されます。これは行政による意図的な情報統制と責任回避の手法であり、監査委員の判断がそれを追認したことを意味します。これにより、解体という行政計画は、もはや引き返すことのできない最終段階へと進むことになりました。
既成事実化される解体プロセス
住民監査請求という、市民に残された法的な異議申し立ての手段が機能しなかったことで、旧体育館の解体は既成事実化されつつあります。行政が一度定めた計画は、市民の声が届かぬまま、不可逆的に進行していきます。その現実が、今、目の前で繰り広げられています。解体計画がすでに最終段階にあることは、以下の事実が示しています。
- 契約の締結: 香川県は10月22日、高松市の合田工務店と8億4700万円で解体工事の仮契約を締結済みです。
- 最終承認の段階: 今後、県議会の議決をもって本契約が正式に結ばれる予定となっています。
県議会からは「粛々と進めて」ほしいという声すら上がっており、本来、行政を監督すべき議会がそのチェック機能を放棄し、執行部の決定を無批判に追認する姿勢を示唆しています。これは、市民や専門家がどれだけ理を尽くしても、一度動き出した行政の歯車を止めることが極めて困難であるという、地方自治における構造的な問題そのものを露呈しています。
問われるべきは「判断の妥当性」
今回の住民監査請求棄却は、単なる一つの行政手続きの完了ではありません。それは、文化遺産の保護、行政の透明性、そして市民参加のあり方という、現代社会が抱える普遍的なテーマに対して、重大な問いを投げかける出来事でした。監査委員は「請求人の主張には理由がない」と結論付けました。
しかし、監査委員はその結論を導くために、「総合的考慮」といった曖昧な言葉で論点をすり替え、自ら「透明性の不備」を認めながらもそれを不問に付すという、論理的矛盾を重ねました。
この一件は、行政が一度方針を固めた事業に対し、市民が異議を唱えることの困難さと、その声を客観的に検証するべき監査制度が、行政に対するチェック・アンド・バランス機能として形骸化していないかという、根本的な問題を白日の下に晒しました。
丹下健三による歴史的建築物の解体が確定しつつある今、問われるべきは、失われるものが建物そのものに留まらず、理を尽くした市民の声に行政が耳を傾けるという民主的プロセスの信頼そのものであるという事実です。そしてそれこそが、今回の決定から私たちが学ばなければならない、最も痛烈な教訓です。

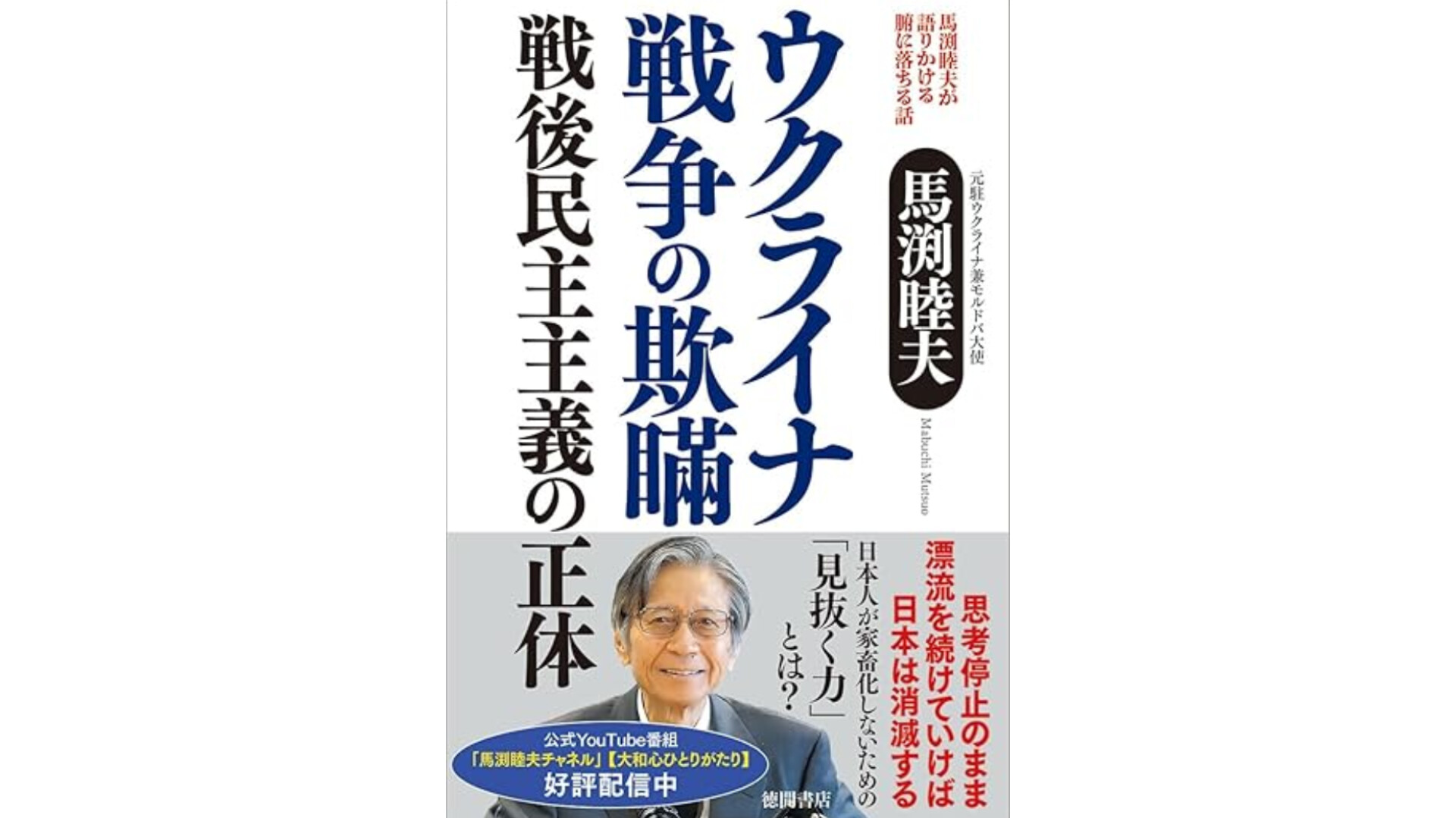

人気記事