北海道倶知安町のニセコは、かつて羊蹄山を望む静かな農村だったが、今や世界の富裕層が集まる国際スキーリゾートに変貌している。ヒラフ地区では、英語の看板が並び、高級ホテルやコンドミニアムが立ち並ぶ。ヒルトンやパークハイアット、リッツカールトンに加え、2027年にはアマンも進出予定だ。1部屋数億円の「MUWA NISEKO」のような物件は、住居ではなく金融資産として取引され、3〜5%の利回りや円安ヘッジを目的に投資家に人気だ。
しかし、この「ニセコバブル」は地元住民に影を落とす。不動産価格は東京23区並みで、1LDKの家賃は15〜20万円に高騰。地元住民の平均年収では家を買うどころか借りるのも困難だ。賃貸は民泊に転用され、スーパーや保育園は減少し、介護施設は賃金不足で閉鎖。地元民は住む場所を失い、静かに町を去るケースが増えている。
地元和菓子店の店主は、賃金高騰による経営難を語る。冬場のヒラフエリアでは時給2,000円が当たり前で、商品価格の値上げを余儀なくされている。地元住民は「ここはもう私たちの町じゃない」と感じ、観光地化の裏で生活環境が失われている。
ニセコの魅力は、軽く乾いたパウダースノーと、外国人でも制限なく不動産を購入できる日本の制度にある。2000年代初頭は東京の10分の1以下の価格だった物件も、香港やシンガポールと比べ割安で、投資対象として注目される。しかし、開発過熱のリスクも露呈。香港系企業による「New World La Plume Niseko Resort」は資金難で工事が停止し、計画は頓挫した。
この現象はニセコに限らず、富良野や美瑛でも進む。観光地化で地価が急騰し、農地が別荘地に変わる中、地元住民は排除されつつある。観光は町を潤す一方、利益は外資に流れ、福祉や教育への還元は限定的だ。ハワイや沖縄でも同様の問題が起き、観光依存の歪みが浮き彫りになる。
地元住民は変化に対応しつつ希望を見出そうとしているが、ニセコの現状は「誰のための町か」という問いを突きつける。観光は救世主か、それとも町を飲み込む脅威か。日本各地の未来を映すニセコの物語は、私たちにその答えを求めている。

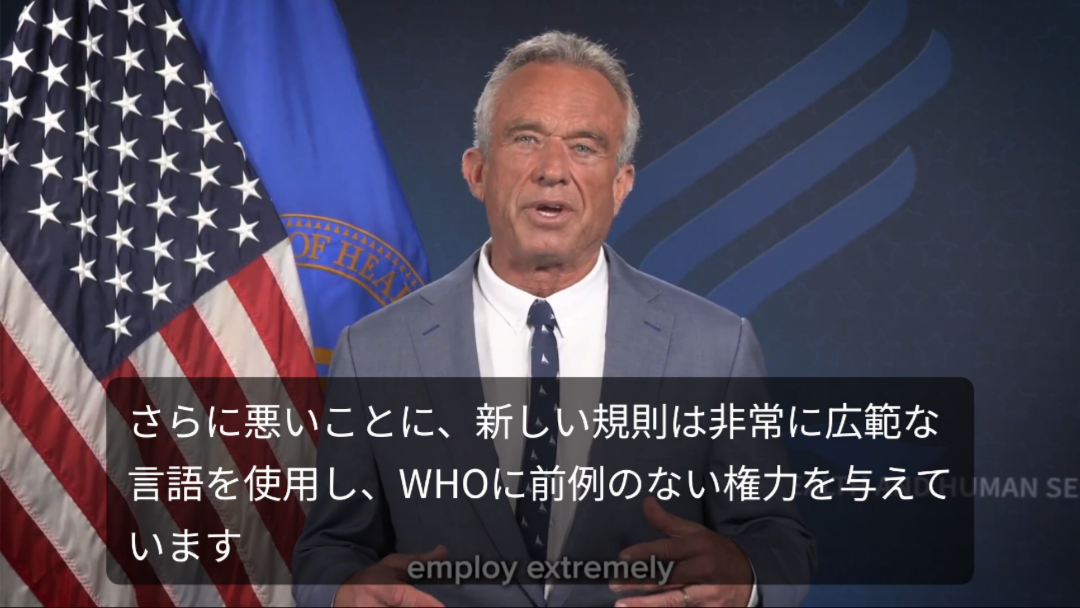

人気記事